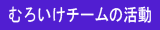No.148 シオカラトンボ
くろんど園地では多くのトンボを見ることができますが、腹部が白色の粉で覆われたような体のトンボをよく見かけます。シオカラトンボです(写真1)。皆さんもよくご存じのトンボと思います。今回はシオカラトンボとその仲間について紹介します。

トンボ目トンボ科の昆虫で、体長が5cmほどの中型のトンボです。白い粉が塩辛昆布の塩のように見えるということでシオカラトンボという名前になったようです。白い粉が見られるのは成熟したオスで、メスは全く違う色をしています(写真2)。ムギワラトンボという名前を聞いたことがあるかもしれませんが、シオカラトンボのメスの呼び方です。知っていないと同じ種類とは思えないですね。

ただし、未成熟(羽化したばかり)のオスも麦わら色なので注意してください(写真3)。
オスとメスとは体色以外にはお腹の先の形状でも見分けられます。近づかないとわかりにくいですが、オスには2本の爪のような付属器と呼ばれるものが見えます(写真4)。本当は下側にもう1本あり、合計3本の爪で交尾のとき(写真5)などにメスの頭をつかみ連結します1)。一方、メスの方は1本ですが、これは産卵管ではなく、尾毛(びもう)と呼ばれる器官で、産卵管は腹の下側についています。
シオカラトンボの成熟したオスはなわばりを持つようになるので、水場の周りを周回して近づいてきた別のトンボを攻撃しているところを見ることがあると思います。このようななわばり行動をするのは昼間だけで、夜は池の近くの林の木の葉にぶら下がって寝ているようです2)。
皆さんもどこかでトンボのメスの産卵シーンを見たことがあると思います3)。オスとメスがつながって産卵する場合やメス単独で産卵する場合がありますが、シオカラトンボの場合はメスが単独で産卵します。ただ、オスも近くで見張っていると思いますので、メスの産卵シーンを見かけたら、周りをよく観察してみてください。メスはお腹で水面を叩いて産卵しています。
幼虫は皆さんご存じのヤゴ4)ですが、写真がないので参考にURLを示しておきます。私が子供のときはヤゴを飼っていたのですが、もしヤゴを育てる機会があればその食事姿をよく観察してみてください。折りたたまれていた顎(あご)が伸びて、イトミミズなどのエサを捕まえます。一瞬なので見逃さないようにしてくださいね。
ところで、白い粉をふいたようなトンボは実はシオカラトンボだけではなく、シオカラトンボの仲間のトンボに共通の特徴になっています。くろんど園地では他にオオシオカラトンボ、シオヤトンボという2種類のトンボも生息しています。見分け方は下記を参考にしてみてください。
●翅のつけねの色(オス/メス共通の見分け方)
無色:シオカラトンボ
黒色:オオシオカラトンボ
黄色:シオヤトンボ(他の2種よりも早い時期に現れる)
●お腹の白い領域(オスのみの見分け方)
白と黒い領域が半分くらい:シオカラトンボ
お腹の先の方だけ黒い:オオシオカラトンボ(全体に青みが強い)
ほとんど白い領域:シオヤトンボ
シオカラトンボは日本各地で見られ、くろんど園地でも5月から9月頃まで見ることができます。水辺を飛び回ってケンカをしたり、メスが立ち姿で飛びながらお腹を水に打ち付け産卵しているところを見てトンボの生態に触れてみてください。トンボが生きていくためには水場が必要です。トンボがこれからも生活していけるように皆さんも園地の水場を大事にしてください。
1) 付属器の本数はトンボの種類で異なり、イトトンボの仲間は2本で、メスの首を捕まえる態勢をとります。逆にいえば、付属器が2本の場合が首で、3本の場合が頭というように捕まえるところで本数が変わっていることになります。
2) 新井 裕、(2013) 「トンボの不思議」 丸善出版
3) 産卵シーンはよく見るのですが、動きが速いためいい写真がありません。今後はビデオ撮影で紹介したいと思います。
4) yagopedia/図鑑
(2025/5/6 大西)
【追加】 シオヤトンボとオオシオカラトンボの交尾シーンを撮影することができたので追加しておきます。オオシオカラトンボの産卵シーンを動画で撮影して画像を抽出しましたのであわせて追加しておきます。
【国内レッドリスト情報】
シオカラトンボ:現時点、沖縄県で絶滅危惧Ⅱ類に指定
 NPO法人 日本パークレンジャー協会
NPO法人 日本パークレンジャー協会