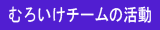No.3 危険動植物の役割
私たちは、参加者に対して催しの始めに野外での危険な動植物について注意をします。ハチ(特にスズメバチ)やマムシ、ヌルデやウルシなど。人に危害を与える生きものはいつも悪者扱いされています。しかし彼らが太古の昔に生まれてから今日に至るまで、地球上に生き残っているのは自然界で果している役割がある筈です。そこで彼らが生態系の中でどんな働きをしているのか考えて見たいと思います。

①スズメバチ
ミツバチは蜜を取るために有用です。また花粉を運ぶ昆虫として良く知られています。一方スズメバチの子は昔から蛋白源として人に珍重されてきました。スズメバチは色々な虫を狩り、それを団子状にしてハチの子に与えます。しかし自らは狩った餌は食べることなく、ハチの子が分泌する栄養物をもらいます。スズメバチは様々な昆虫やその幼虫を捕えますが、結果それらの昆虫が増えすぎないように数量調節をしているのです。

②マムシ
マムシは乾燥したものを滋養強壮剤として用いたり、また焼酎漬けにしてマムシ酒にされます。マムシはカエルや昆虫などを餌にしますが、その結果これらのものが増えすぎないように数量調節をする働きをしています。
春にはオタマジャクシをたくさん見かけますが、マムシがいなければ水辺はカエルだらけになるでしょう。マムシ自身はタカなどの野鳥の餌になっています

③ ウルシ、ヌルデ、ハゼ
ウルシやヌルデ、ハゼはかぶれるので嫌われますが、ウルシの樹液は漆塗りの材料に用いられます。(英語で日本のことをJapanと言いますが、もともとJapanはウルシと言う意味です)
なお英語で中国をChinaといいますが、もとは中国が陶器(china)の生産国であったことに由来しています。
ハゼの実からはロウがとれローソクが作られます。お隣の韓国ではウルシやヌルデの新芽は山菜として食べられます。ヌルデの実は生薬「塩麩子(えんふし)」として下痢に効くといわれています。またウルシやヌルデの実は野鳥の餌として食べられますが、種子は野鳥によって遠くに運ばれます。
こうして考えると嫌われ者の危険動植物ですが、人に危害を与えようとして生きているわけではありません。自然の生き物は、それぞれに役立ちを持ち互いにつながって生きています。
参加者に注意をする時、彼らの危険性だけではなく役立ちの面も伝えて色々な生き物がいることの大切さを伝えたいものです。(た2013.Aug)
 NPO法人 日本パークレンジャー協会
NPO法人 日本パークレンジャー協会