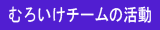No.147 ムラサキサギゴケ
春の一日、近くにまだ残っている田んぼに出かけてみました。畦道を歩くと色々な野草が見られます。ジシバリ、ハコベ、ヘビイチゴ、キュウリグサ、カンサイタンポポ、オオイヌノフグリ、ハハコグサ、ムラサキサギゴケ、トキワハゼなど..。まるで小さなお花畑のようです。
畦道に咲く野草たち
畔道の花畑にはムラサキサギゴケの群生がありました。
※ムラサキサギゴケは花の形がサギが飛んでいるように見え、匍匐枝(ほふく
し)を出して苔のように広がるのでこの名がついたとされています。
一方ムラサキサギゴケによく似たトキワハゼも同じ場所に咲いています。
さて下の写真1と2は、どっちがムラサキサギゴケでどっちがトキワハゼでしょうか?
写真1 写真2
ムラサキサギゴケとトキワハゼ
写真だけ見ても違いが分かり難いのでそれぞれの特徴を比較してみました。
| 花 | トキワハゼ | ムラサキサギゴケ |
| 花の色 | 白い | むらさき色 |
| 花の大きさ(2者比較) | 小さい (≒10mm) | 大きい (20~30mm) |
| 上の花びらの切れ込み | 浅い | 深い |
| 広がり方 | 群生せず上に伸びる | 横広がりで群生する |
| 花期 | 冬を除き年中 | 3~6月 |
※実際には花期により単独で生えていたり、群生していない時もあるので注意
ムラサキサギゴケの雌しべは花粉を食べる?
ムラサキサギゴケの花は、写真3のように花びらの中央に白い盛り上がりが二筋あり、オレンジ色の斑点があります。その周りには毛が生えていて、この斑点は虫たちに花の蜜の在処(ありか)を教える標識となり、毛は虫が止まる足場になります。 雄しべは左右に2本見えますが奥の方にも2本あり、雌しべは上下に口を広げたような形をしています。
ところで、ある本にムラサキサギゴケの雌しべに花粉が付くと「閉じる動作をする」と書いていたので本当にそんな動きをするのか試してみました。
写真4のように口が開いた雌しべに草の茎など細いもので軽く触れると、すぐにその口が閉じて行くのが観察できました。(写真5)
この動きは実際にミツバチやハナバチが花粉を付けて吸蜜に来た時、ハチが雌しべに触れて花粉が付くとすぐ口を閉じて花粉を閉じ込めることになります。これは、まるで雌しべが花粉を食べるようにも見えて面白い動作です。
野の小花の世界にはハッとするような色や模様の美しさ、奇妙な形や動きがあり実に面白いと思います。あなたもルーペを持って観察に出かけましょう。
余談ですが、トキワハゼの写真をよく見ると、ムラサキサギゴケと同じように花の奥に雌しべが開いたようなものが見えています。今度トキワハゼを見たら雌しべの形とその動作を調べてみたいと思います。ムラサキサギゴケと同じょうな動きをするのでしょうか?
2025/4/23 (T.T)
 NPO法人 日本パークレンジャー協会
NPO法人 日本パークレンジャー協会