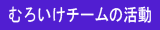No.153 ハラビロカマキリ
逆三角形の頭に前あしが鎌の昆虫といえば、そう、カマキリ(英名;Mantis)ですね。共食いなど動くものなら何でも食べることで悪名が高い昆虫です。今回はくろんど園地でもよく見かけるハラビロカマキリ(写真1)について紹介します。

カマキリ目カマキリ科の昆虫で、他のカマキリに比べて腹部が広いのでハラビロカマキリと呼ばれています。成虫の前翅には白い紋がついているので他のカマキリと簡単に区別できます。草原よりも林縁(樹上)に生息しているカマキリです。緑色だけではなく、褐色のハラビロカマキリもいます(写真2)。

カマキリは不完全変態の昆虫なので幼虫も親と同じ体形をしています。ハラビロカマキリの幼虫はおしりをあげた態勢でこちらを睨むのですが、威嚇のポーズなのでしょうか(写真3)1)。子供のときは恐ろしいカマキリもなんだかかわいいですね。

園地を散策しているときに葉の上などで写真4のような物体が残っているのを見たことがないでしょうか。カマキリの抜殻です。抜殻2)は軽いので風で飛ばされたり、雨で落ちてしまったりするのですが、よく見ることができるので、皆さんも探してみてください。

10月頃になるとお腹の中からハリガネムシ3)がでてくる場面に出くわすことが多くなります。他のコラムでも紹介されているので参考にしてください。
秋になり葉がなくなるとカマキリの卵のうを見つけやすくなります(写真5)。オオカマキリの卵のうは高さのあるおむすびのような形ですが、ハラビロカマキリの卵のうは平べったく、お稲荷さん型で、突起が残っていることがあるので区別することができます。カマキリがいない時期でも卵のうの形を見ることでどのようなカマキリが生息しているのかがわかりますね。
ハラビロカマキリは関東以南で見られ、くろんど園地でも6月頃から幼虫が見られるようになり、9月頃には成虫を見ることができます。秋の行楽で山に出かけたときは探してみてください。
1)オオカマキリの幼虫はおしりを上げるポーズはしません。コカマキリの幼虫はおしりを上げるようです。
2) オオカマキリの抜殻の可能性がありますが、おしりが上がった抜殻ということでハラビロカマキリと考えました。
3) ハリガネムシ目に属する生物で、日本には14種類知られているそうです。
(2025/9/5 大西)
 NPO法人 日本パークレンジャー協会
NPO法人 日本パークレンジャー協会